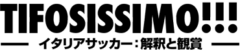ハリルホジッチ解任煽り騒動に向けて、今から6年前、2010年の南アフリカW杯を終えた時点で『エル・ゴラッソ』に寄せた日本代表総括を。岡田武史監督は、就任以来コンパクトな陣形を高く押し上げたハイプレス戦術を基本に据えてチーム作りを進めながら、本番直前のスイス合宿で、ラインを下げて自陣で守備を固める専守防衛に路線変更、結果的には組織的な守備力を武器にしてグループリーグ突破を実現したのでした。しかしこうして振り返ると、この当時と比べて今の方がずっと「世界との距離」は縮まっているように見えますよね。
![]()
ワールドカップ4試合を通じて明らかになった「日本の現在地」をひとことで表せば「守備は世界に通用したが、攻撃は全然通用しなかった」ということになるだろう。
4試合で2失点(しかもPKとミドルシュート。最終ラインを崩されての失点はゼロ)という堅固なディフェンスは、出場国中屈指のレベルにあった。10人をボールのラインより後ろに戻して連動性の高いプレッシングを行い、決してフリーの敵を作らせない組織的な守備戦術の質の高さ、そしてそれを90分(どころか120分)持続させた運動量は、守備に関しては一家言持つイタリアのコメンテーターたちをも感嘆させた。
問題は、その守備力が攻撃を全面的に犠牲にすることでしか成立し得なかったところにある。それを客観的に示すのがFIFAの公式スタッツだ。1試合平均の総パス数は出場32カ国中31位、パス成功率(60%)は最下位の32位、平均ボール支配率は42%。攻撃の指標はほとんどが出場国中最低レベルだった。
まあ、少なくとも9人、しばしば本田も含めた10人をボールのラインより後ろに戻し、深いラインを敷いて守っているのだから、そこで奪ってもそう簡単に敵陣にボールを運べないのは道理である。しかし、日本が現在地よりも先に進むためには、現在の守備力を保った上で、そこに攻撃の「量」と「質」を上乗せして行くしかない。
攻撃の「量」というのは、端的に言えばボールポゼッションのことだ。日本人はテクニックとアジリティと運動量に優れるからその持ち味を活かすべき、と言われてきたが、少なくともテクニックに関しては、認識を改める必要があるだろう。厳しいプレッシャーの下、時間とスペースのないところではパスを3本つなぐことすらままならない。これが、このW杯が示した現実だ。
アジアレベルではなく世界レベルの厳しいプレッシャーと速いプレーリズムの中で、スピードのあるパスを正確につないで攻撃を組み立てるためには、何よりもベースとなる個人技術・個人戦術のさらなる向上が必要だ。
あえて挑発的な言い方をすれば、アジアはともかく世界を相手にしたときには「ポゼッションサッカー」などまだ遠い夢でしかないし、「決定力不足」を云々するのは10年早い、まずは厳しいプレッシャーを受けてもボールをつなげる基礎技術の向上を、というのが、このW杯から日本サッカーが学ぶべき教訓だと思う。
攻撃の「質」に関しては、個人と組織の2つの側面がある。もし日本に本田レベルのタレントがもう2、3人いれば、現状のままでもベスト8までは行けただろう。単独で違いを作り出すことができるタレントの有無は、絶対的なチーム力に直結している。
実際、GS突破は本田の存在なしでは不可能だった。「守ったら点が取れず攻めたらやられる」というジレンマを日本が克服できたのは、本田が前線で孤立しながらもそのキープ力でチームが押し上げる時間を稼ぎ出し、純粋な個人能力で2ゴール1アシストをもたらしたから。守備の固さは組織力の賜物だが、攻撃は彼の力が全てだった。
組織という観点では、ボール奪取能力の向上(今大会の守備は、相手の攻撃を食い止めるための守備であり、積極的にボールを奪って逆襲に転じるためのそれではなかった)、奪った直後の展開のスピードアップ(カウンターの質向上)など、戦術的な課題は少なくないように見える。□
(2010年6月25日/初出:『エル・ゴラッソ』)