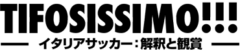ウルトラス関連シリーズの4回目。まだもう少し続きます。
![]()
下の『ビジネス化の波がフーリガンを追い詰める』で、紙幅の関係で触れられなかったのが、ウルトラス/フーリガンと政治の関係である。
70年代にウルトラス/フーリガンのムーブメントが生まれた当時から、ヨーロッパのゴール裏は過激な政治運動や団体とつながりを持ち続けてきた。当時のゴール裏は極右と極左に二分されていたが、これは政治状況がそうだったからだ。60年代いっぱいで“政治の季節”が終わってしまった日本とは異なり、ヨーロッパでは70年代に入っても若者文化やカウンターカルチャーが、政治と密接に結びついていた。
イタリアでは少なくとも90年代初頭まで、ほとんどのゴール裏が「赤」(極左)と「黒」(極右)にはっきりと色分けされていた。「赤いクルヴァ」の代表は、トリノ、ミラン、ジェノア、フィオレンティーナ、リヴォルノ、ローマなど、「黒いクルヴァ」の代表はヴェローナ、アタランタ、インテル、ユヴェントス、サンプドリア、ラツィオなど。
しかしこの構図は、“政治の季節”がヨーロッパでも終わりを告げ、ベルリンの壁崩壊によってコミュニズムが歴史的役割を終えて極左の政治運動が変質を余儀なくされた90年代初頭以降、徐々に変質していく。
実際の政治運動と同様、ゴール裏でも極左が勢力を失い、「赤いクルヴァ」の多くは政治色を薄めるか(例えばフィオレンティーナ、ミラン)、あるいはその内部で勢力を強めてきた極右勢力に乗っ取られる形で黒く染まっていった(ローマ)。2007年現在、イタリアのゴール裏はほとんど「黒」(極右)と「白」(ノンポリ)の二色に塗り分けられているといえる。
ヨーロッパの若者文化から、左翼的な政治運動とのつながりが消えてしまったわけではない。しかし90年代後半以降の左翼運動は、反グローバリズム、反核、エコロジー、ゲイカルチャーといった方面に向かっており、ゴール裏の(というかサッカーの)マッチョで男根主義的なカルチャーとは相容れない、むしろ対極に位置する文化圏を形成している。
一方で極右の方は、ネオナチやネオファシズムが民族主義、土着主義と結びつく形で、人種差別、反移民、反ユダヤ、文化的純血主義といった従来の主張をますます強めており、それどころか旧東欧諸国で広まっている排他的民族主義に見られるように、かつての極左の武闘派勢力までも糾合してしまったように見える。
そして、この極右政治勢力とゴール裏とのつながりは、イタリアに限らずヨーロッパ全域で広く見られる現象となっている。
ゴール裏で暴徒化する「フーリガン」の多くは、ヨーロッパの格差社会の中・下層に位置するワーキングクラスであり、徒党を組んで暴力を働くという行為が、そうした不満や困難のひとつのはけ口になっている、という話は別の原稿でも触れた通り。
ヨーロッパにおけるウルトラス/フーリガンのムーブメントを研究しているイタリアの社会学者ヴァレリオ・マルキは、彼らを特徴づける要素として、「社会に対する不満や失望」、「強烈なテリトリー意識」、「社会的承認に対する強い欲求」という3つを挙げている。
社会的な不満や困難を抱えている層が、ゴール裏というテリトリーを治外法権化して自らの聖域とし、マフラーやTシャツといった所属を示すアイテム、そして示威的な暴力行為を通じて社会に存在を誇示する、という構図である。
「社会では落ちこぼれ、スタジアムでは英雄」(マルキ)という、その後半部分が彼らのアイデンティティになっていると同時に、その前半部分には、政治のつけ入る隙がある。政治との接点はまさにそこにある、というのが、フーリガン研究における共通した視点になっている。
あらゆる政治活動の原動力が、社会に対する不満や異議にあることは論を俟たないが、それだけでは、なぜ極右なのかという説明はつけにくい。接点のひとつとして考えられるのは、極右が主張する排他的な民族主義は、都市・地域に根ざし、それを代表していることをアイデンティティの根幹としているサッカークラブ(名称にほぼ必ず都市名が入っているのは偶然ではない)とそのサポーターにとって、ごく自然に受け入れられるロジックであるということ。
民族主義と地域主義、土着主義というのは、発想としてほとんど同根である。ウルトラスがアイデンティティとして持つ土着主義(都市ベース)のメンタリティは、日常生活の中での反移民感情、人種差別感情を媒介にして、極右の民族主義的主張に抵抗なくリンクしているように見える。
スタジアムにおける黒人選手へのモンキーチャント、ユダヤ系選手への差別や攻撃から、ハーケンクロイツやケルト十字(ネオナチ、ネオファシズムのシンボル)までの距離は、ほんの小さなものでしかない。ゴール裏が極右という政治運動に自然に取り込まれているとすれば、理由のひとつはそこにあるような気がする。■