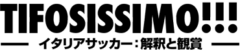レオナルド来日記念特集も第4弾まで来ました。前回に引き続き、2011年1月のインテル監督就任時のテキスト。こちらはfootballistaの連載コラムに書いたものです。
![]()
「私はロマンチストだ。仕事がほしかったわけではなく、強い刺激、大きな夢、困難なチャレンジを探していた。ミランを辞めた時に、監督という仕事を続けて行くべきかどうか深く考えた。この仕事はとても濃密でデリケートだから。
でもインテルからオファーが来た時に、これこそが自分が本当にやりたかったことだとわかった。今この時、インテルの監督を引き受ける以上に大きな挑戦は他にはない。サッカーはほんの一瞬の間にすべての感情を生きる機会を与えてくれる。喜び、怖れ、不安、幸福感……。インテルはこれらすべてであり、限りないチャレンジだ」
12月28日の就任記者会見で語ったこのコメントに、レオナルドがインテルの監督を引き受けたすべての理由が凝縮されている。
このコメントにある通り、ベルルスコーニとの軋轢が原因であと1年残っていたミランとの契約を昨シーズン末で解消した時点では、今後も監督としてキャリアを送って行くかどうか、まだはっきりとは決めかねていたようだ。2014年のブラジルW杯に向けて代表監督、あるいは組織委員会の要職に就くことを求められれば応じる用意がある、と表明したのもその頃のこと。
しかし、ブラジルサッカー協会からは何のオファーも来ないまま時が過ぎ、レオナルドは8月末にコヴェルチャーノ(イタリアサッカー協会のテクニカルセンター)でUEFAプロコーチライセンスのコースを修了した後、英国のSKY、フランスのCanal Plusで解説者を務めながら次の機会を待つ、モラトリアム的な「浪人生活」に入っていた。
ミランの監督退任が決定的になった昨年4月末、筆者は当コラムでレオナルドの今後について取り上げ、「ミランの監督“ごとき”で終わるような器ではない」として次のように書いた。
「プレーヤーとしてもエグゼクティブとしても世界トップレベルの舞台で経験を積み、母国語であるポルトガル語に加えて英語、フランス語、イタリア語、スペイン語(と片言の日本語)を操るマルチリンガルな国際人。サッカー界の現在と未来に対する明確なビジョンと、それを実現するために必要なリーダーシップ、交渉力、忍耐力、そして謙虚さを備え、その視野はサッカーの世界に留まらず社会全体にまで及んでいる――。これだけの資質と能力を備えた人材は他には思いつかない。将来はプラティニに匹敵するプラネット・フットボールのリーダーになってくれることを期待してしまう」
監督という職務に与えられた権限は、レオナルドがこれまで蓄積してきた様々な経験と知見を最大限に活かすには、あまりにも限られたものであるように見えた。
ミランの指揮を執ることになったのは、カカとアンチェロッティが去り、しかもベルルスコーニ会長が赤字補填をストップするという難しい状況の中で、クラブの立場と利害を理解してこの過渡的な状況を乗り切れる監督が必要という特殊な事情からだった。監督就任の可能性が噂に上った当初は「私はベンチよりもデスクからサッカーを見る方が性に合っている」と語っていたし、断り切れずに指揮官の座を引き受けてからも、監督という仕事は彼の終着点ではなく、もっと大きな何かを目指すために積んでおくべき経験のひとつに過ぎないように思われた。
しかし、世界的なトッププレーヤーとして、ワールドカップからスクデット、コパ・リベルタドーレスからCLまで、あらゆるタイトルを経験してきたレオナルドにとって、プレーの「現場」であるピッチを舞台とし、サッカーというゲームがもたらすあらゆる感情をダイレクトに生きる機会を与えてくれる監督という仕事は、スポーツエグゼクティブという理性的な職務からは決して得ることができない、フットボーラーとしての本能を直接揺さぶる麻薬的な魅力があるのかもしれない。
興味深いことに、レオナルドは、9月に『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューに応えてこんなことを語っていた。
「モラッティとは何年も前から付き合いがある。親愛の情に基づく利害の絡まない関係だ。でもイタリアには『絶対にないとは絶対に言えない』という諺があるからね。ミランとの関係は永遠に続くようにも思われたけれど、終わりが来た。今年はミラニスタとしてではなくニュートラルな視点で物事を見ることを学ぶ時期になるだろう」
もちろんこの時点では、3ヶ月後に本当にインテルからオファーを受けることになるとは想像すらしていなかっただろうが……。
ミランを率いたレオナルドは、ロナウジーニョ、パトというブラジル人タレントの潜在能力を最大限に引き出すために、「6人で守って4人で攻める」攻守完全分業型のシステム「4-2-ファンタジア」をひねり出し、前監督アンチェロッティの時代とは明らかに異なるアイデンティティをチームに与えた。しかし、今回のインテルでのアプローチは、それとは180度異なるものだ。
「インテルはすでにでき上がったチームだ。自らのアイデンティティを思い出すだけで十分だ。私は何も新機軸を打ち出すつもりはない。ただ選手たちがベストの力を出せる環境を整えるだけだ。このチームに必要なのは、多くの勝利を挙げいくつものタイトルを勝ち取っていた当時の自信と落ち着きを取り戻すことだ」
前任者ベニテスは、モラッティ会長からチームの選手たちまで、インテルのすべてにつきまとうモウリーニョの幻影と戦わなければならなかった。戦術コンセプトから毎日のトレーニングメニューまで、モウリーニョのそれとは明らかに異なるメソッドを持ち込むことで新たな刺激を与え、新しい時代のページを開こうと試みたし、クラブの内外誰もがそれを彼に期待していた。
しかし、蓋を開けてみて明らかになったのは、モウリーニョがインテルに残した遺産(あるいは爪痕)はあまりにも大きく、それを正面から否定するようなやり方はモラッティ以下誰にとっても、理性、感情の両面で受け入れ難いものだったということだ。
攻守の切り替えに焦点を合わせたトランジションサッカーからボール支配によって主導権を握るポゼッションサッカーへの戦術コンセプト転換と、すべての練習メニューでボールを使いマシンを使った筋トレを否定するモウリーニョ流のフィジカルコンディショニングから従来型のボールを使わないフィジカルトレーニングへの回帰。ベニテスが打ち出した2つの新機軸を、インテルは一度も納得して受け入れることがなかった。キヴが試合中に戦術的な問題でベニテスに食ってかかったり、エトーやスタンコヴィッチが途中交代時に不満を露にしたりと、監督とチームが全面的な信頼関係で結ばれていない兆候は、シーズン序盤からすでに明らかだった。
レオナルドは、こうした状況を逆手に取るかのように、当初からモウリーニョに対するリスペクトをはっきりと打ち出し、その路線継承を明言した。そればかりか、モウリーニョに助言を乞うていることを隠そうとすらしていない。
「モウリーニョに電話をしたのは、彼を経由せずにインテルで仕事を始めることは不可能だったからだ。ここには今もあらゆる場所にモウリーニョを見出すことができる。それは正しいことだ。私が彼の意見に基づいてスタートしたのは、彼はとてもインテリジェントで、このクラブについてすべてを知っているから、そのスピリットを今もここに残しているからだ。私はモウリーニョを真のフオーリクラッセ(超一流)だと思っている。彼が貴重なアドバイスをたくさんくれたことを心から幸せに思っている」
ある意味でこれは、自分がモウリーニョの「正統な後継者」であることを主張しそれを周囲に受け入れさせるための、非常に戦略的でしたたかな振舞いだということができる。戸惑いと混乱が支配していたインテルをひとつに結束させ、それを率いて行く求心力を手に入れるためには、モウリーニョの遺産を継承するのが最も賢明かつ堅実なやり方だ。しかもモウリーニョ本人の「お墨付き」まで取っているのだから、これはもう申し分ない。
だが、一見すると計算ずくに見えるこの振舞いも、レオナルドにとっては同時にしごく自然なものであるようにも思われる。このところの彼やモウリーニョの発言から伝わってくるのは、彼らが心から互いを認めリスペクトし合っているということ。2人の間には対抗心とか嫉妬とかいう感情はまったくないようにすら見える。レオナルドは、誰に対しても(モウリーニョやベルルスコーニに対してすら)そういった感情を抱く必要を持たず、常に100%自然体で振る舞う「自由」な人間だ。そしてそれが彼の本当の凄さでもある。おそらくモウリーニョもそれをよくわかっている。
ミランで前任者のアンチェロッティに対して同じようにリスペクト溢れる姿勢を取ったレオナルドは、結果的にまったく異なるアイデンティティをチームに与え、誰もが期待した以上の結果を残した。果たしてインテルは数ヶ月後、どんなチームになっているだろうか。そう考えるだけでもわくわくしてくるのは筆者だけではないはずである。□
(2011年1月15日/初出:『footballista』連載コラム「カルチョおもてうら」